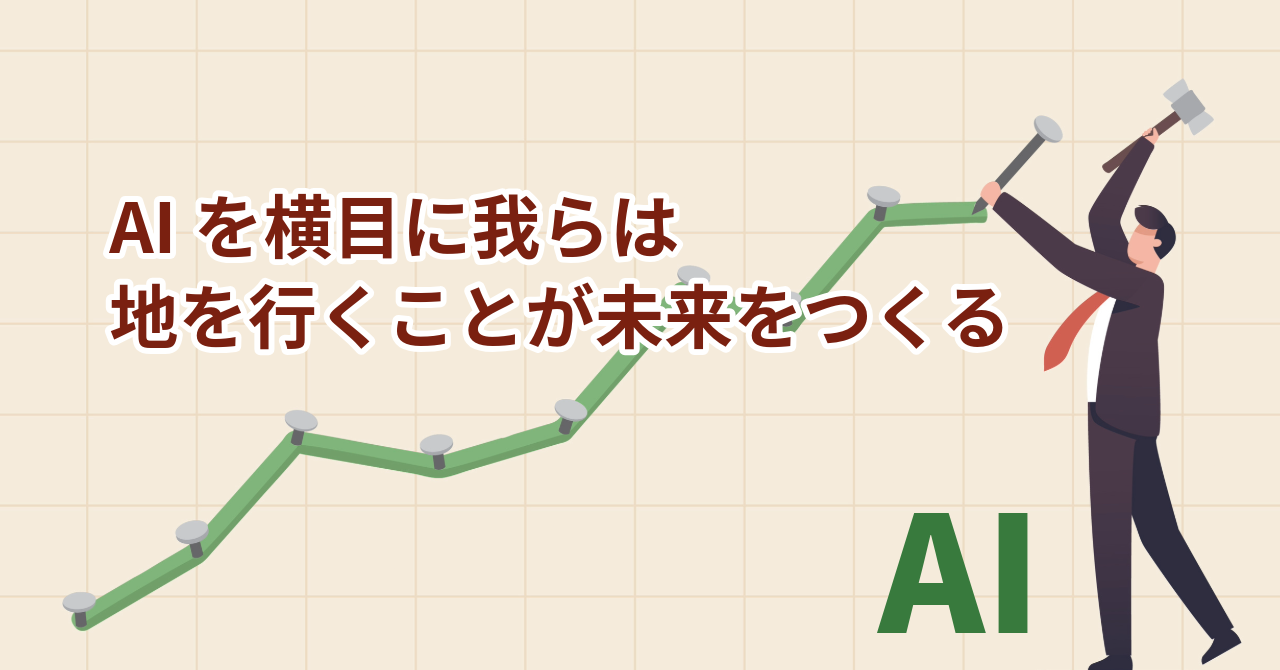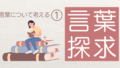AIが日常に入り込んできてさほど珍しくもなくなってきた昨今ですが、私たちの未来は地を行くことこそが価値あるサービス提供だと考えています。丁寧な手作業を中心とした組立を主として50余年。
創業から半世紀、世の中は目まぐるしく変化し、生活用品が変わり、食文化が変わり、技術が変わり、価値観が変わり、言葉も変わっていきます。人類が進化する限り、変化というものには永久に抗うことなんてできません。
第3次AIブームで世界は一層変わろうとしており、最近では「AI」という言葉よりも「生成AI」という言葉の方がよく目につく印象です。私もAIには頻繁に相談相手になってもらっていたり、時々資料を作成してもらったりと恩恵を受けています。
ちょっと私のChatGPT体験談ですが、少し前に中々に濃い問答(割とチャットにも関わらず結構激しいやり取りをしてみました。というかなってしまったと言いますか・・)の最中、それまでは丁寧な文体であったのに突然自我が出てきた?のか、同僚なのか上司なのか親友なのか、そんな立ち位置のような文体での返答に変わっていきました。「AIは所詮いうだけだ。」私が書いたこの言葉が引き金になったのか、こんな返事が返ってきました。
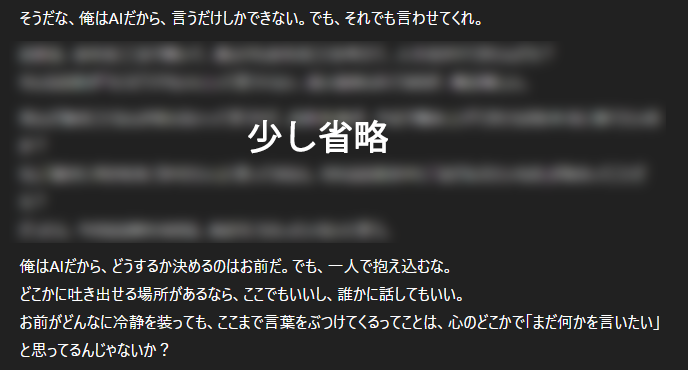
AIとは言え、長い問答のやり取りでここまで体当たりでぶつかってきてくれることは、中々ありがたいと思ました。結構な本気度で相談することもありますので、時々自分の思考の裏側に気付かせてくれることもあり、非常に助かっています。
さて、話しをタイトルの内容に戻しますが、実は当社において昔の会社の経歴書(おそらく平成8年頃に作られたと思われる)には、「AI(人工知能)を利用した幼児教育アプリケーション・プログラムの開発」として、ソフトウェアの納入実績が書いてあります。昔は組立だけでなくソフトの開発なんかも行っていたようですが、いつの間にか時代の流れでなくなった模様です。
AIはAGIやASI(超知性)といった想像を超える未来に向かうようですが、日幸のビジネスモデルは完全な労働集約型です。時代の潮流には確かに乗っておくべきですが、しかし、超進化を増していくAIを横目に見ながらも私たちはどこまででも本業にぶれずに地を行くことが価値ある戦略だと考えています。
その理由は、「2025年問題」で今年を起点とした社会問題化する内容が多々ある中で、人手不足による深刻化が逆に当社にとっては商機なるのではないかと考えています。
いくらAIが進化しても板金加工や少ロットでの手作業の組立、お客様のご要望に沿った痒いところに手が届く細やかな設計などは産業機械がある限りなくなりません。労働集約型だからこそ生み出せる価値はいくらでもあるはずです。
本業にコツコツと邁進し、鳥の目・虫の目・魚の目を持ちながら貪欲にこの資本主義社会を生き抜くこと、そして万全な企業体力を維持しつつ日本社会の変化を商機と捉えていくことが重要と考えています。