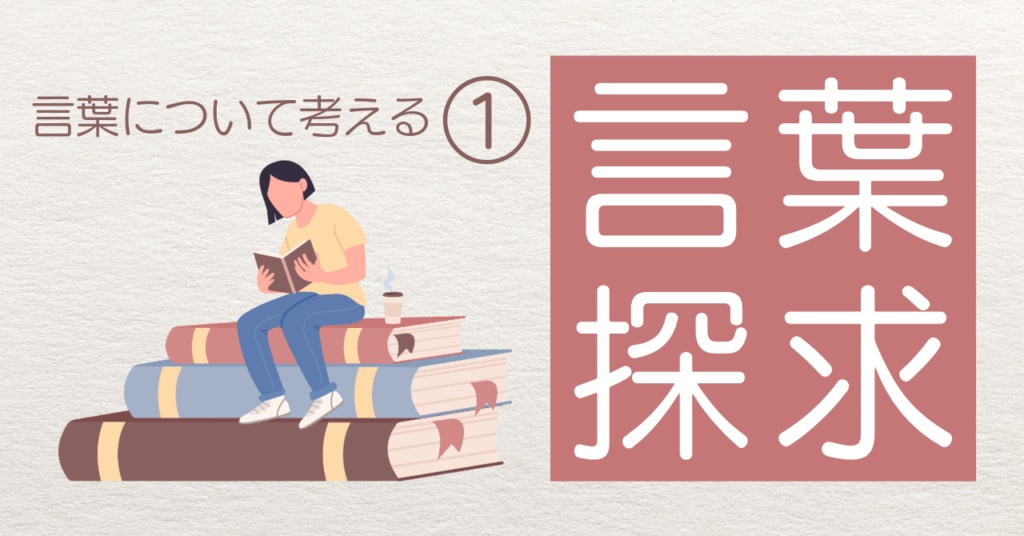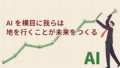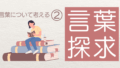とても面倒な内容になると思いますが、とても大切なことだと思うので書いてみたいと思います。
時々、色々な人との会話の中で「言葉の大切さ」について話をする機会があります。
ここぞというときにはその「言葉」にしっかりと向き合ったほうがいいというお話です。なぜなら言葉によって世界は作られていますし、世界は言葉で成り立っています。動物と人間が決定的に違うのは、言葉を操れるようになったことでその言葉に「意味」というものを吹き込み、それを共通認識してコミュニケーションをとっているからです。
少し古いですが、ユヴァル・ノア・ハラリ氏の「サピエンス全史」の漫画版を数か月前に読みました。(本は大分長い)20~40万年前にホモサピエンスが誕生し、ネアンデルタール人とホモサピエンス、進化の末にホモサピエンスが生き残り私たちの祖先となりました。なぜホモサピエンスだけが、つまり私たちだけが生物界の頂点に立てたかという理由は「集団で同じ思想を持つことができたから」のようです。
ネアンデルタール人は家族くらいの集団しか形成できなかったのに対し、ホモサピエンスは家族の人数を超えた集団を形成することができ発達してきました。そこには集団で同じ思想というか宗教観(宗教観という言葉よりも共同思想といった方がいいのかもしれません)みたいなのが生まれたらしいというのが理由のようです。例えば個人的に想像するのは、獲物を見つけた時に声を出さなくても複数人でアイコンタクトだけでお互いの意思を確認できたり、同じ事柄を見ただけで笑ったり手を叩いたり(拍手のような)することができるようになったからかもしれません。
そこから長い年月をかけて言葉や文字が発達し、グーテンベルクの活版印刷ができるようになってから一気に世界中で文字を使ったコミュニケーションが広まっていき情報社会が誕生しました。(一気に時代は飛びますが)
さて、タイトルにある「言葉のふわふわさ」ですが、言葉って話したら消えてしまいますから言葉そのものは物体として存在せずただの音です。この、ただの音だけで私たちは情報を交換しているということに改めて人間とは驚異的な能力を持った動物であると私は解釈しています。言葉で世界は作られているってまさにそうで、言葉がなければ家も建ちませんし、火の扱い方も分かりませんし、お互いが一緒に何かをすることはできません。
例えば「心」という言葉も、心というものの実態はありません。触れないし見ることもできませんが、「心が大切」とか「心に聞いてみる」とか「心ない言葉」とか。では一体「心」って何でしょうか?心を説明する言葉もきっと実体のない言葉で説明されますね。もう一つ例を挙げると、サービスを提供する際に必ずでてくる「品質」っていう言葉。品質向上とか品質が悪いとか。そもそも品質って何でしょうか?っていう問いとそれによる回答がなければ、私たちは「品質」というものを捉えられませんし、共通認識を持つこともできません。
では、そんな実態のない言葉と組織の中で働く私たちは、どんな向き合い方をすべきなのでしょうか。
次回も言葉のふわふわさを例に挙げながら、今回の続きを書きたいと思います。